- なんか子育てがうまくいかない…
- 失敗しない子育て方法を知りたい!
- 子育てに失敗する理由はなんだろう
こんなお悩みを解消する記事です。
私は「子の連れ去り」という、親権制度に起因する社会問題の当事者です。ふたりの息子たちとの親子時間はわずかしかありません。人や社会の本質的な「育ち」に興味が強く、学びと実践をくり返して6年目になります。
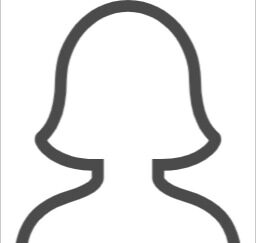
極少時間で息子たちと良好な親子関係をつむぐ私が、「失敗する子育てのパターンや注意点」を解説していきます。社会問題の当事者だからこそ見える、子育てに失敗してしまう社会背景も書き添えます。
子育てがわからなくなっているあなたは、読み終えるとかなりスッキリするはずです!
失敗する子育て3パターンとは?
【自己肯定感と自己効力感】

失敗する子育ては次の3パターンです。
- 愛することも責任も教えない
- 愛することだけ教える
- 愛することを教えずに責任だけ求める
解釈しだいで失敗は回収できるので、「遠回りする子育て」といえそうです。また、子育ての目標を「子どもの自立」と定義したとき、親が子どもにできることは次の二つの力を育むことでしょう。
- 愛する力
- 責任の力
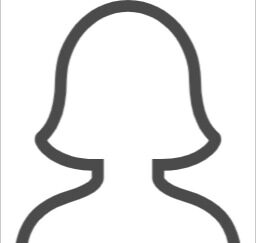
責任の力=自己効力感
人の自立を支えてくれるのは、 「愛する」と「責任」のふたつの力です。なので上述した3パターンを、失敗する子育てとしてあげています。
3パターンに共通する特徴は、問題を認識できずに親と子の課題を分けられない状態です。親の課題を子どもの課題にしたり、子どもの課題を親の課題にしたりします。自分がどんな問題に陥っているのかを、親自身が理解できていないからです。
順にみていきましょう。
失敗する子育て①愛することも責任も教えない
自分を愛せずに自信もなく、なにもできないと思い込んでしまう状態になります。 愛する力も責任の力も弱くて、自己肯定感も自己効力感も育まれていないからです。

めんどいし
子どもが自立するための子育てを親が放棄しているので、もはやネグレクト。親の生きづらさを子どもにそのまま伝えているといえるでしょう。親もまた、放棄された子育てで大きくなった可能性が高いです。
子育て放棄の問題は時間をおいて顕在化しやすく、小中高で不登校になったり、成人後に引きこもりなったり、 毒親の子が毒親になったりして現れます。子どもの成長と共に、子育てに手がかかってゆくパターンといえそうです。
失敗する子育て②愛することだけ教える
自分を支える土台となる自己肯定感はあるけれど、自信を持ちにくい状態になります。 責任を学んでいないと自己効力感が弱く 、問題を解決する能力が乏しくなるからです。
成長するにつれて、やりきる力やあきらめない力のなさが目立ちはじめます。自分の意見をもつことやはっきり伝えることが難しく、周囲の顔色をうかがう癖がつきがちです。
親が「自由」と「放置」を勘違いしているケースもあります。
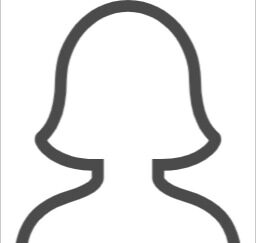
責任を知らないと挫折が多くなるので、せっかく育んだ自己肯定感がしぼむかもしれません。もったいないです。
挑戦と失敗をくりかえしながら、小さな成功体験を積むことで、人は自信をつけて「責任の力」を備えてゆきます。
失敗する子育て③愛することを教えず責任だけ求める
安心できない環境で常に責められている状態になります。 愛することを知らないと、自己肯定感がなくて不安が強いです。結果、責任を学ぶための問題に立ち向かって、課題を見つけて解決する経験を積めません。
一般的な日本の子育てのありかたといえそうです。「自分がない」状態で「すべきこと」だけ詰め込まれて、なぜか「失敗」が許されない環境になります。
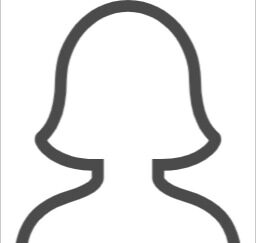
失敗しない子育てへの注意点
【自己肯定感と自己効力感】

繰り返しになりますが、失敗しない子育ての注意点はたったふたつで「愛する」と「責任」です。「自分は大丈夫!」と「自分はやれる!」の感覚を養えるように、親は子どもをサポートしましょう。
- 愛する→自分は大丈夫!→自己肯定感
- 責任→自分はやれる!→自己効力感
「自分は大丈夫!」は自己肯定感になる
「自分は大丈夫!」の感覚は自己肯定感のある状態です。親から「愛する」子育てを受けた子どもは、根拠がなくとも安心感をもちます。
ありがちなのが、親が「愛する」つもりで「愛される」ためにする子育てです。子どものためにと勘違いして、自分の欲求を満たすための関わりをしていないかを、親は注意するといいでしょう。
親が子どもの絶対的な心のよりどころとなっていれば、「愛する」子育てができているといえそうです。何があっても親は自分の味方だと信じて、子どもが遠慮せずに親へ意見できるような状態です。子どもに意見させようとするのではなく、意見できる土壌を大人が整えているかがポイント。
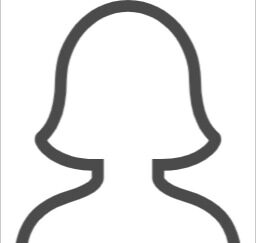
「自分はやれる!」は自己効力感になる
「自分はでやれる!」の感覚は自己効力感のある状態です。親から「責任」を学んだ子どもは、問題を解決する力があるので、人生の逆境にくじけないメンタルをもっています。
また、無条件に愛してくれる親がいれば、子どもの自己肯定感は育まれてゆきます。そして、自己を肯定できる安心感が強い子どもは、失敗を恐れずに挑戦できるので、いろんな問題とぶつかって解決方法を次々に学んでゆけます。
幼少期の挑戦と失敗の繰り返しが「自己制御=責任」の学びとなり、自己効力感が育まれていくのです。
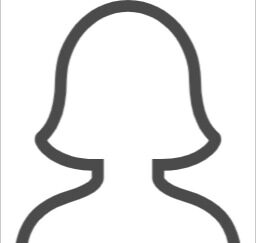
私の説明ではいまいちわからん!という方は、「お母さんの自己肯定感を高める本」「 子どもの自己効力感を育む本 」を読むとスッキリします。Kindle Unlimited でならただいま無料!
失敗する子育てと社会の影響

失敗する子育てに深く関係するのが日本の「親権制度」です。親権制度は親子の枠となるシステムで、社会の基盤制度だから。つまり、私たち日本人の価値観の源泉といえるでしょう。そして、日本社会は失敗する子育てを30年以上続けています。
「社会の成長」の失敗は「子育て」の失敗
だから、もし子育てがうまくいかなくても、自分を責める必要はありません。社会全体で失敗する子育てをくり返しているだけです。子育てしにくい社会で子育てを試行錯誤しているのだから、むしろ自分をめちゃんこ褒めてください。
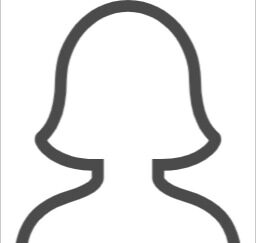
▶敵意帰属バイアスで夫婦仲崩壊?原因や改善策を知ってストレスを減らそう
失敗の再生産を続ける高度成長期と長期停滞期
失敗する子育てが色濃くなってきた時代背景を追っていきます。
- 高度成長期→母性力に偏る
- 長期停滞期→母性力と父性力の混同
- 崩壊衰退期→わけわからん
ココで重要となるのが、高度成長期と長期停滞期の子育て背景となる「単独親権制度」です。当時の未来、つまり今の社会を支える子どもたちの育てられ方が、まさに単独親権制度による捻じれた価値観のなれの果てといえます。
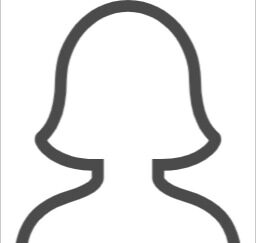
子育てに必要なのは「母性力」と「父性力」
子育てに必要な力は、絶対的な愛を育む「母性力」と問題に立ち向う力を育む「父性力」です。人生のステージは大きく分けると、「安心する場所」と「挑戦する場所」のふたつ。たとえば「家族」と「社会」です。
私たちは安心できる場所があるから、挑戦できる場所へといけます。生きる力を育めるのは相互の行き来があるからです。なので子育てに必要な力はコレ。
- 安心の母性力(家族)=自己肯定感=愛する力
- 挑戦の父性力(社会)=自己効力感=責任の力
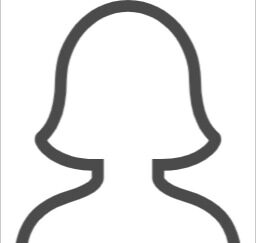
単独親権制度の「性別役割分担」の概念
単独親権制度には「母性力」と「父性力」を明確に分ける概念があります。「子育て=女性」「仕事=男性」の性別役割分担です。
子育てを「愛する」と「責任」を育てる「子どもの自立」と考えるのであれば、理にかなった役割分担になります。自己肯定感には愛する力を育む「母性」が必要で、自己効力感には責任の力を育む「父性」が必要だからです。
親は子どもを、包み込むように母性力で愛し、突き放すように父性力で責任を学ばせます。この繰り返しで子どもは「自分は大丈夫!」「自分はやれる!」と成長して自立へ。
単独親権制度はその役割を女性と男性の「性別」でしています。そして、性別役割分担が子育てに適するように、機能していたのが戦前戦後あたりの時代。
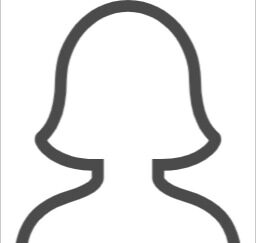
子育て概念が捻じれる高度成長期と長期停滞期
日本の転換期となる高度成長期と長期停滞期では、家族の形態が大きく様変わりします。核家族化や共働き世帯の増加です。しかし、家族のカタチをつくりだす親権制度は変わらずに、単独親権制度のまま。
単独親権制度は家制度を継承する、大家族向きのシステムです。
また、単独親権制度は「婚姻」と「出産」を紐づけます。つまり、私たち日本人の価値観は「結婚して子どもを産む」となります。なので晩婚化と未婚化がすすむ日本で、現行の親権制度を使っている限り、加速度的に少子化してゆくといえます。
社会の「実態」と「システム」が捻じれた結果、2023年の沈みゆく日本ができあがったのでしょう。
高度成長期の子育て環境は母性力まかせ
高度成長期は父性力の欠ける子育て環境になります。主に母性力だけで子育てする時代です。
結果、子どもたちの「責任の力」が弱りはじめ、自己効力感の乏しい世代を築くことに。
経済の発展により男性の仕事負担は増え、専業主婦が主流となり、家庭内での「性別役割分担」が確たる価値観となります。 一方で、女性の進学率も社会進出もこの時期に増えますが、単独親権制度の家父長制の価値観が残る社会では女性の地位は低いままです。
抑圧された社会で、親は必死に子育てと仕事をしますが、抑圧されていることにすら気づかずに、間違いの再生産をくり返し続ける社会が完成する!?
長期停滞期の子育て環境はぐっちゃぐちゃ
長期停滞期では父親の子育て参加が推奨されはじめます。母性力と父性力の混同がはじまって「子育ての空洞化」へ突入です。
社会では「子育て=女性」の概念がまだまだ根強く、子育て環境は整わないままなので親の学びが進みません。従来の母親の仕事を、父親が担う意識は増します。しかし、おむつを替えたり食事を作ったりするのは、大切とはいえ表面的な子育てです。
子育ての本質は「愛する力」と「責任の力」を親が子に育み、子どもの「自己肯定感」と「自己効力感」を高めること。
表裏一体の本質が偏ると、ズルズルと両方がダメになっていきます。つまり「子どもの自立」を育めない社会へ。それが、たぶん、2023年の私たちの国。
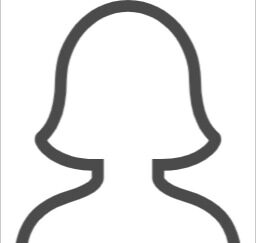
▶共同親権とは?【日本再生の希望】現状の問題点やメリットデメリット
子育てで一番大切なこと

まとめます。
親が「自分の人生」をしっかり歩めば子は育つ
親は自己実現を楽しみ、学び、ただただ子どもを愛して、子どもの挑戦を見守るのみです。繰り返しになりますがポイントはたったふたつ。
- 愛する母性力で→自己肯定感アップ
- 責任の父性力で→自己効力感アップ
子どもの人生は子どものものです。
子どもは親の所有物ではありません。
子どもに親のヘルプは不要です。
親は子どもの最強サポーターであれ。
まずは親のあなたが自己肯定感をアップ!
学ぶほどに心は育まれてゆくでしょう。
私もまだまだがんばります。
きっと大丈夫。
あなたもがんばって。
【おすすめ関連本】

松村 亜里 WAVE出版2020/2/15
kindle版1,485円→0円

松村亜里 WAVE出版2020/3/14
kindle版1,485円→0円
\\無料体験30日!解約も簡単 //
▶読み放題 Kindle Unlimited
▶聞き放題 Audible
【おすすめ関連記事】
▶自己肯定感を1年で幼少期分高めた感想/おすすめの方法も厳選!
▶自己肯定感とはどういう意味?子育てから定義すると簡単スッキリ






